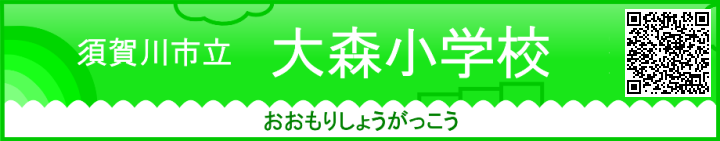


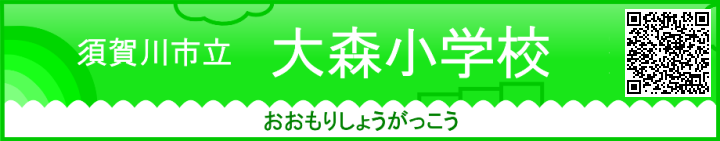

6月19日(水)、市の環境課の方にお出でいただき、3・4年生がESD教育の出前講座を受けました。ESDとは、Education for Sustainable Development の頭文字をとったものであり、日本語では「持続可能な開発のための教育」となるそうです。
まずは「3Rについて学ぼう」ということで、環境課の方が、映像などを通して3Rに関する説明をしてくださいました。
3Rに関する質疑応答の後は「ごみの分別ゲーム」です。準備された模擬のゴミを「可燃ごみ」や「不燃ごみ」、「資源ごみ」等に仕分けするゲームでした。
続いては「ごみ投入体験」です。我々は「ゴミ収集車」と呼びますが、業界用語では「パッカー車」と呼ぶとのこと。パッカー車の仕組みや操作について教えていただいた後、いよいよごみの投入体験です。大量のゴミを苦も無く押しつぶすあのプレス機のパワーを目の前にすると、大人もたじろいでしまいますが、子ども達は2人組になり、ごみ投入係とパッカー車の操作係に分かれて体験しました。やってみるとなかなかの重労働。しかも実際のゴミはもっと重く、きっとにおいもきつい上、1日に数百件の家の分のゴミを集めて回るのだから、たいへんな重労働であることが分かります。
この体験を通して、子ども達は持続可能な未来のために、リデュース=ごみの発生や資源の消費自体を減らす、リユース=ごみにせず繰り返し使う、リサイクル=ごみにせず再資源化する、という3Rの考え方の大切さを感じ取ることができたことでしょう。次はその未来のために何かアクションを起こしていかなければなりません。3・4年生のみなさん、がんばりましょう。
〒962-0723
福島県須賀川市狸森字杉内90
TEL 0248-79-2188
FAX 0248-89-1771